夏休みが終わり、熱気に満ちた中学の校舎に、再び日常が戻ってきた。しかし、私の「体操服生活」は途切れることなく続いていた。むしろ、拍車がかかったと言っていい。9月は学校中が運動会一色になるからだ。
夏休み中は、さすがに体操服で毎日を過ごしていたのは運動部員がほとんどだっただろう。文化部の生徒たちは、各々の部活動に応じて私服や練習着を着ていたはずだ。しかし、運動会が近づくと、状況は一変する。全校生徒が体操服を着用する機会が、強制的に増えていくのだ。
朝礼台に立つ体育教師の声が、校庭に響き渡る。 「さあ、お前たち! 運動会まであと少しだ! 気合い入れていくぞ!」 その声に呼応するように、私たちは体操服姿で隊列を組み、行進の練習を繰り返した。白と紺の体操服が、一糸乱れぬ動きで校庭を埋め尽くす。まるで巨大な体操服の波のようだ。
文化部の友達も、この時期ばかりは体操服姿で汗を流していた。美術部のユウコは、いつもはおしゃれな私服で絵を描いているのに、この日は体操服の襟元を気にしながら、不慣れなムカデ競争の練習に必死だ。吹奏楽部のケンタも、楽器を置けば体操服で組体操のフォーメーションを確認している。
「あー、また体操服かよ」 誰かがぼやいた。だが、その声には諦めと、どこか慣れのようなものが混じっている。夏休み中に私たちが体感した「体操服からの解放」を知らない文化部の生徒たちでさえ、この運動会前の強制体操服期間によって、体操服が日常に溶け込んでいく感覚を味わっているようだった。
放課後の部活動も、運動会練習に多くの時間を割かれる。体育館でも校庭でも、誰も彼もが体操服姿で、一心不乱に練習に打ち込む。汗が生地に張り付き、肌の感触と一体化する。その感覚が、もはや違和感ではなく、当たり前のものとして体に馴染んでいた。
夜、家に帰ってシャワーを浴びた後、また洗い立ての体操服に袖を通す。パリッとした綿の生地が心地よい。 「明日もまた体操服でしょ」 母の声が、まるで呪文のように私の耳に届く。その言葉に逆らうことなく、私は丸首の紺色ラインに再び首を通し、ブルマーを穿いた。胸の校章が、夜の闇に浮かび上がる。まるで、学校からの見えない支配が、寝ている間も私を包み込んでいるかのようだ。
ベッドに潜り込むと、布団の感触と共に体操服の生地が肌に触れる。その感触が、なぜか私を落ち着かせた。今日一日、体操服で過ごし、体操服で練習に励み、そしてまた体操服で眠りにつく。この繰り返しが、私の中に確固たる秩序を築き上げているようだった。
学校という閉鎖的な空間の中で、私たちは皆、体操服という同じ拘束衣を身につけ、同じように汗を流し、同じように練習に励む。文化部の生徒でさえ、運動会を境にこの**「体操服の共同体」**に組み込まれていく。その一体感が、私たちに奇妙な安心感を与えていたのかもしれない。
私服に着替えることが「自由」だと知っていても、体操服を身につけることの「楽さ」と「安堵感」には抗えなかった。それは、強制された状況下で、抵抗を諦めた者だけが知り得る甘い蜜のようなものだった。
9月、全校生徒が体操服に身を包み、運動会という共通の目標に向かって突き進む。その光景は、私たちの中学生活が、いかに体操服というアイテムによって色濃く染め上げられていたかを象徴していた。そして、私はその支配の中に、変わらぬ快感を見出していたのだった。


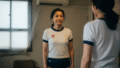

コメント